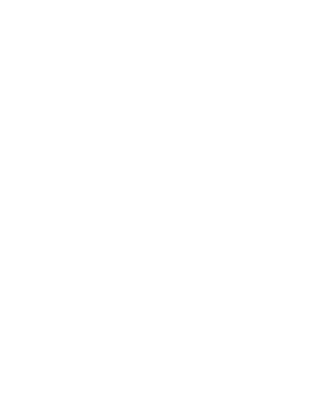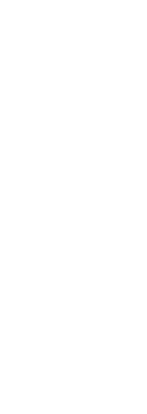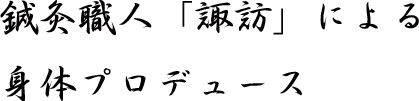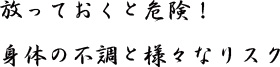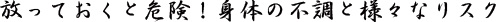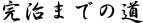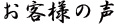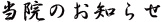体調不良対策について_押上・錦糸町の鍼灸院
こんばんは、押上・錦糸町の鍼灸。びわの葉治療院の諏訪です。
桜も開花し始めました。
これから、どんどん咲き乱れると期待したのに・・・
明日は、又寒い上に雨だとか・・・。
この時期、妙に気分が乱れがちな方を良く目にします。
自分もそう感じる今日この頃。
特に、精神に不安を抱えていたりする場合はこの時期は辛いと思います。
精神科や心療内科に行けば、
何らかの診断名をつけて薬でも頂けそうですが・・・
しかしながら、病院に行くほど深刻な状態でないのに、
この時期にイライラやドキドキ感、それに伴う頭痛や無気力感を抱く方も少なくありません。
今回は、その様な診断未満の不定愁訴を東洋医学的視点から解き明かしてみようと思います。
季節変化に体が反応する
春夏秋冬と自然界は変化します。
冬なら体力の消耗を防ぐために、毛穴を閉口させ、内臓に気血を蓄える。
夏なら気血をよく巡らし、毛穴を開き、体熱を溜め込まない様にする。
とこの様に、身体も季節変化に対応しています。
しかし、
春秋の変化は結構体に堪えます。
春は、寒から温。
秋は暑から涼という変化。
いずれも体温・水分調節には何かと苦労がいります。
大気も不安定になり、雨風が多くなる季節でもあります。
この微妙な水分変化が体内の関節内圧や気血流動に微妙な変化をもたらします。
春の邪気に注意
春先では、冬の寒と春の温が混ざり、
「寒湿」という邪気を生み出します。
「寒」は物を固める性質をもつ。
「湿」は水気を帯び物質を粘らせ動きにくくする性質を持ちます。
以上の特性から、
「寒湿」タイプの疾患は、
移動性の症状ではなく、限定的な症状が特徴的です。
例えば、
脳、筋肉・関節などに「寒湿」が溜まればどうなるか?
脳では、思考・忍耐・行動などの部分に悪影響を及ぼし、
イライラや落ち着きの無さ、かったるいという感じを持つかもしれません。
筋・関節に溜まれば、機能障害が生じます。
腫れの少ない関節痛や筋の強ばり感など運動障害に繋がるのです。
そして、春にはもう一つ、
「風」もあります。
これはこれで厄介。
今回はこの辺にて・・・
「東洋医学から診る:季節変動は精神変化に注意」
本日は当ブログをお読みいただきありがとうございました。
押上 錦糸町 鍼灸院 びわの葉治療院です。