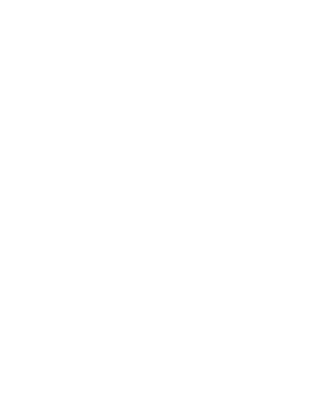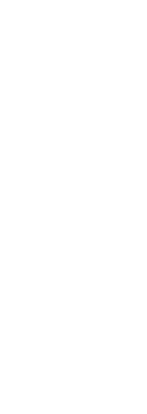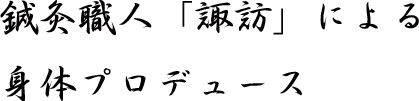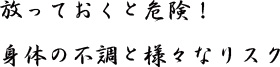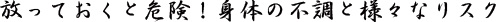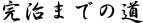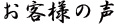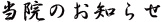体調不良対策について_押上・錦糸町の鍼灸院
こんばんは、押上・錦糸町の鍼灸。びわの葉治療院の諏訪です。
暑い毎日が続きます。
水分補給を忘れない様にしましょう。
多汗の陰に内臓の冷えあり
汗と内臓がどう関係しているの?
という疑問を持たれるかもしれません。
西洋医学的に言えば、
汗は体温中枢による調整でなされるもの。
つまり、暑ければ脳が体温調整の為、
体内水分を排出して、温度調節を図る。
脳がコントロールしている事であります。
医師に汗をかき過ぎると相談しても、
数値的に問題がなければ、
適度な運動と栄養バランスを指導されるかもしれません。
でも、これで良くならなかったらどうするのか?
診かたを変えてみるのも必要です。
東洋医学(中国医学)では、
汗は血の一部とされます。
特に勝手にこれら液体が体外排出するのは、
何かが失調しているからに他ありません。
その何かとは・・・
「気」
です。
何でも気か~と思われるかも知れませんが、
東洋医学とは気が基本要素なので仕方ありません。
でもこの気を注意深く見ると、
様々な機能が存在する事がわかります。
その中でも、
この様な問題には、
気の固摂作用が大きく関わっております。
この「固摂作用」、
イメージとしては、形や状態を止めておくという感じ。
汗も必要以上出るのは、
固摂作用が上手く作動していない状態。
もっと専門的には、
固摂とは、液体や物質の性質を維持し、
必要な物とそうでない物に分別し、
一か所に停滞させずに然るべき所へ動かすという事。
汗かきの人はこれが弱い。
気は内臓から生まれ出るのもです。
故に辿っていけば、内臓にも問題があるのではないか?
という事に行きつきます。
内臓の気が弱っている時は汗をかきやすいのです。
体内では、概日リズムに従って不要な水分は汗や尿として排出されます。
しかし、
疲労過多、睡眠不足、肥甘濃味の過食などが常習化すると、
内臓が疲れてしまいます。
体内(内臓)の機能が弱まると水分代謝が落ちてしまうというわけです。
本来、夜間は内臓に体温が集中するはずが、
内臓に気が帰着しない為、
頭や手先など端に必要以上の体温が集まってしまう状態が発生します。
これを虚熱といいます。
詳しくは五心煩熱(頭両手足5つへの熱)というのですが、
高熱とは異なり、ややボーっとする程の感覚があり、
体温計で測ってもさほど変化しません。
いわば、体感での体温の変化ですので自覚症状でしか分かりません。
そして、
この五心煩熱がおこる事で、
緩い熱の鬱滞が体表に蓄積し、
夜間の大量発汗(盗汗)が起こってしまうのです。
更に、
体内(内臓)は冷えて皮膚表面は火照る感覚を呈する為、
一見すると、熱っぽいので冷たい物を欲しがりますが、
これは避けた方がよろしい。
体内は冷えているので、冷たい物は内臓機能を弱らせてしまうのです。
特にこの状態で、生冷過食をすると、
脾(分解消化吸収)肺(汗孔の解放調節)腎(水分への分離)
の力を低下させ、内臓間のバランスを壊しやすいので注意が必要です。
ではどの様な対応をしたら良いのか・・・
長くなるので、
今回はこの辺に・・・
前回のブログはコチラから
「夜中の異常な汗のかき過ぎが改善:M様(50歳)part1」
完全個室空間でのじっくり治療。
冷え体質の改善!!びわ葉温熱と鍼のプロフェッショナル!!
本日は当ブログをお読みいただきありがとうございました。
押上 錦糸町 鍼灸院 びわの葉治療院です。