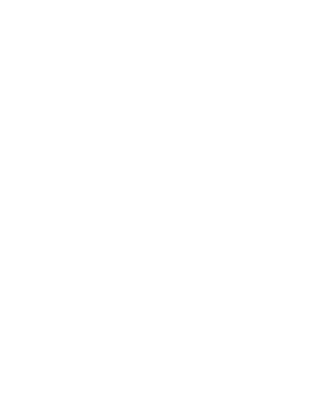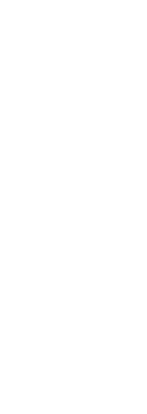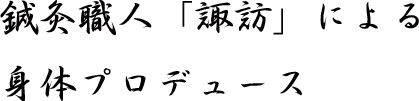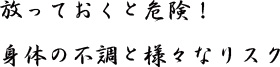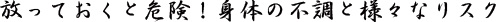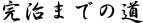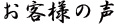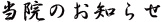体調不良対策について_押上・錦糸町の鍼灸院
こんにちは、押上・錦糸町の鍼灸。びわの葉治療院の諏訪です。
初夏の季節となりました。
梅雨前の季節で過ごしやすい季節です。
びわの実も大きくなり、あと少しで食べ頃です。
子供の頃は木に登って実をとって食べたりしたものでした。
先日患者さんからの質問でびわの実と葉の効能の違いがありました。
今日はその事について紹介していこうと思います。
実は甘いが・・・
びわの実は6月が食べ頃。
黄色から橙色に変化する頃が今の季節。
その実は、ほのかに甘くすっきりとしています。
よく質問されるのですが、
実には薬効はどれ程あるのか?
という事。
葉にあれほど薬効があるので、さぞかし実も相当なものかと想像してしまいます。
実際には、さほど薬効があるわけではなさそうです。
いわゆる、果実としての趣を堪能する方が宜しいかと思います。
今の季節においては、水分を程よく含むびわの実は身体を潤すという意味で非常に適しているといえます。
しかし、実の中の種子は別物。
よく、これを好む方もおられるようですが、
非常に強い効能と危険があるそうです。
実の種子は効能が高いが扱いが極めて難しい
色々な健康雑誌などでも紹介されるびわの種。

健康食品でも取り扱いがあるようです。
効能も葉の3倍はあるのではないかと以前教わりました。
それほど強力なびわの種ですので、
ガンの方などでご存じなのはよく見られます。
しかし、薬効が強力という事はそれだけ体への影響もあるという事です。
あるものの本によれば、
一日の摂取量は3粒以下程。
下痢などの症状も出やすいとの事。
びわの葉もそうですが、
種の中に含まれるアミグダリンと呼ばれる成分には、
青酸配糖体という物質が存在します。
これは口内や胃液の分解酵素により、
シアン化水素いわゆる青酸を生じる自然毒があります。
この毒性は、時間経過と共に減少するようですが、
いずれにせよ、短期で摂取するのはお勧めできません。
それを過剰摂取すると体に悪影響を及ぼすと言われております。
昔は種はガンに効くなど言われ、
よく、患者さんからもびわの種は食べた方が良いか?
という質問を受けるのですが、
中毒性が危険視されるので、
実際患者さんには勧めた事はありません。
病気で体力がない方に、
この毒性が悪影響を及ぼす可能性を考えれば、到底お勧めできようがありません。
ちなみに、この青酸配糖体を含む果実は主にバラ科。
梅、桃、びわなどです。
そもそもこれらの種が何故、青酸配糖体を持つかといえば、
自己防衛の為だったそうです。
ただ、昔から梅干しなども健康保存食として活用しているので、
きちんとした毒抜きの処理工程がなされれば安全に食品として楽しめます。
前回のブログはコチラから
「予防治療の意義 part1」
完全個室空間でのじっくり治療。
冷え体質の改善!!びわ葉温熱と鍼のプロフェッショナル!!
本日は当ブログをお読みいただきありがとうございました。
押上 錦糸町 鍼灸院 びわの葉治療院です。