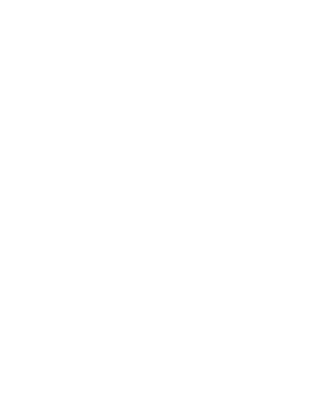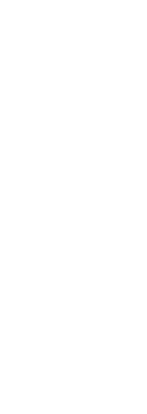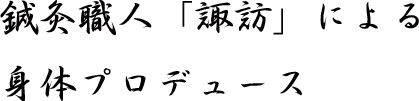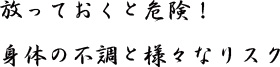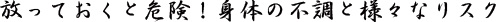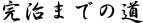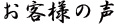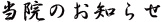体調不良対策について_押上・錦糸町の鍼灸院
こんばんは、押上・錦糸町の鍼灸。びわの葉治療院の諏訪です。
痛くてどうしようもない時、
どんな治療でも治るのなら、何でも受けてみようという気になりませんか?
もし、その様な時に針治療の技術を自分が持っているなら、
私なら躊躇なくそれを使います。
実は、先日から猛烈な腰痛に悩まされており、
寝返りうつのも痛くて、起き上がるのもやっとの状態・・・
腰痛の厳しい時は、トイレで腹圧をかけるだけでも苦しいのです。
どうにもならない・・・
それでも何とか仕事だけはやっていたのですが、
でも、ついにお手上げ・・・
本日仕事の隙をついてようやく自分に治療しました。
困難を極めたのは、自分の腰に針を打つという事。
腕を後ろに回して針を刺すのは本当に難しい事です。
普通なら手は回せても刺せません。
しかもしっかりさせないのでチクチク痛い。
横向きに寝て、腕だけを腰に回し針を打つ。
少しの動作でも、腰には力が入ってしまうので、
腰の力を抜いて、腕だけに集中するのはかなり難しいのです。
でも、痛い所は分かっているので、
ポイントにヒットしさえすれば、痛みが和らぐのは分かっているので、
ちょっと時間はかかりましたがどうにかやり切れました。
患者さんがいつも言う通り、辛い時の針は本当に効きますね。
そんなこんなで、今回は本当に針様に助けられました。
「湿」は難しい
前回は「湿」が体に影響を及ぼすと様々な症状を引き起こす事をご紹介致しました。
実際に「湿」を説明しろと言われると、
濡れているとかジメジメしているとか、
現象的な説明はできますが、
その特性をどう説明したらよいか案外分からないものです。
それもそのはず、捉えどころのない存在です。
「湿」は治療においても難しく、
取り過ぎてもいけない、取らないわけにもいけない。
微妙な存在。
「湿」絡む疾患は、治療も長くかかるのです。
湿気が体に影響を及ぼした時
東洋医学では、「湿」の特性を以下のように説明しています。
「湿」とは、
・体内の水の余りである。
・ジットリと粘性を帯び、経絡上にある気血の停滞を助長する。
・単独でも影響を及ぼすが、大抵は寒、熱を伴った症状が多い。
・重力に従い、重く、鈍く、長期に渡り各部位の下部、末端を犯しやすい。
とあります。
昔の人はよく気が付いたものだと感心します。
症状は、言ってみればスッキリしないものが多いのです。
実際、これを現代の疾患・症状に当てはめてみると、
梅雨時期の粘性下痢・関節痛・リウマチ性関節痛、痛風、痰、水虫、湿疹など
はこの特性がよく当てはまります。
実際、症状も結構当てはまるのではないのでしょうか。
沈思や、精神不安など体の上部でも起こることもあるので、
脳でも湿が絡めば、情緒や思考、血管系でも悪影響は起こりえます。
雨期など、ジメっとした感覚と共に精神混濁があるのは「湿」の影響もあると東洋医学では捉えているのです。
因みに、
春先は「風」の特性ですから、気血が上昇し、乱れますので「湿」とは真逆です。
各々季節性疾患の特性がよく出ています。
この様に実態が捉え難く、中々回復に時間を要するというのが分かります。
治療は寒・熱などの特性に応じて行う
「湿」は、気や血流の流れが鈍い関節部分などに貯留します。
ほとんど動かない為、ずっとジクジク痛かったりと症状が持続しがちで、
実際、動きの切れが悪いなど、体の動きにも影響する事でしょう。
外気湿気の多い時は症状も憎悪するというイヤラシイ存在であるという事。
その証拠に、
運動や事故で関節や古傷が痛むのも湿っぽい時期が多いなどありますが、
「湿」が絡んだ可能性が極めて高いのです。
又、
「湿」の疾患は時期によって大きく変化します。
精神不安や思考停滞など「湿」単独で起こる事もあるのですが、
実質的に痛みの有無がはっきりしている場合が多く、
大抵は、寒・熱を伴います。
秋や冬の雨、冷房、冷えた物などで痛みが持続するなら「寒湿」と呼びます。
熱感を伴う痛みがあれば、「湿熱」と呼び、やや痛みが激しい。
治療法も、
西洋医学とは異なり、痛みを抑える方法も異なります。
本体である「湿」を解消するには、
まず、連結している「寒」「熱」から解消しなければなりません。
熱性が強ければ、針を用い、
寒性が強ければ、灸や温熱療法を用います。
それと同時に気血の停滞を解き、湿を流していきます。
いわゆる、目下の問題を解決しつつ、
最終的に本体である「湿」をうまく流していくという方法がとられるわけです。
そもそも、「湿」も体の一部。
水が解消されずに、余った物ですので、「湿」を生み出した原因を改善し、
上手く気血に乗せて解消させてあげなければいけません。
その様にして、マイルドに治療して自然解消させていくのが東洋医学なのです。
次回は、体の内部ので生じる「湿」について、
「湿」を生み出しやすい原因をご紹介してまいります。
前回のブログはコチラから
「この時期特有の「湿気の病」part1」
完全個室空間でのじっくり治療。
冷え体質の改善!!びわ葉温熱と鍼のプロフェッショナル!!
本日は当ブログをお読みいただきありがとうございました。
押上 錦糸町 鍼灸院 びわの葉治療院です。