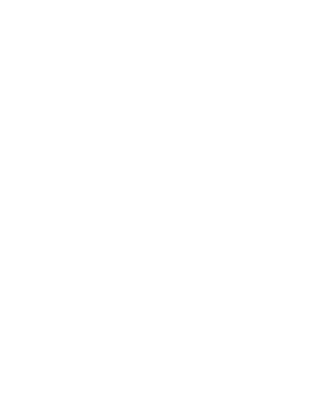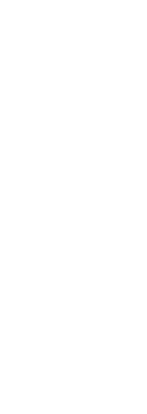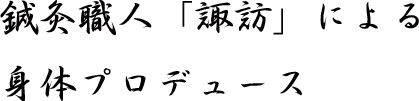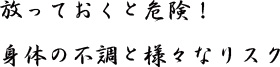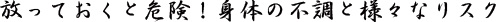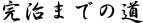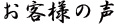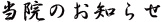体調不良対策について_押上・錦糸町の鍼灸院
こんばんは、押上・錦糸町の鍼灸。びわの葉治療院の諏訪です。
新年が始まって、そろそろ世の中も動き始めました。
でも、体の方は大丈夫でしょうか?
・休み明けで中々調子が上がらない。
・年末年始、食べ過ぎで胃腸の調子がまだ本調子ではない。
そんな方に是非お勧めしたいのがコレです。

本日のテーマは「七草粥」です。
1月7日といえば七草粥ですね。
春夏秋冬にそれぞれ七草があり、その時期の物を食べて気を養うとされています。
日本の伝統的食文化であり、正月の祝善祝酒で弱った胃腸によいとされていますね。
ここでは、春の七草と効能を紹介したいと思います。
「春の七草」とは?

せり (セリ)
なずな(ペンペン草)
ごぎょう( ハハコグサ)
はこべら(コハコベ)
ほとけのざ(コオニタビラコ)
すずな(カブ)
すずしろ( ダイコン)
すずな・すずしろは冬の定番食材ですが、後の5つの食材はほとんど食べる機会がないかもしれませんね。
「作り方」
1月6日の夜に七草をしゃもじや包丁の背で叩いて細かく刻んでおく。
7日の朝に塩と七草を混ぜて粥にする。
「効能」
せりは体温を上げ、発汗作用を促し胃腸の機能を活発にする。
なずな・ごぎょう・はこべら・ほとけのざは血圧を下げ、血液を浄化し、五臓を整える。
すずな・すずしろはおなじみのカブ・大根ですね。
これらは、酵素やビタミンを豊富に含み、栄養価も高く胃腸を整える効果がありますね。
簡素ですが非常に消化の良い健康的な食材と言えますね。
そもそも、七草粥は古代中国からの習わしで年の初めの7日目に7つの若菜を食べて無病息災を願ったとされています。それが、日本では七草を入れた粥として定着したそうです。
昔の人は、季節の物を利用して五臓を整えていく方法を知っていたのですね。
東洋医学でも季節の物を食べる事の重要性が説かれています。
それは単に栄養素だけの観点からだけではなく、季節の植物は生命力(気)を多分に含んでいる。
その気も含めて取り入れる事で、心身の気を補充強化するという意味合いも含まれています。
いわゆる、初物を食べるというのもその様な事から生まれたといえます。
だから、季節外れの物を摂る事は避けるというのも頷けます。
洋食やグルメな食事が多い中で、こういった伝統的な食事を食べる機会が少なくなってきています。
この季節でしか味わえない伝統食を楽しみながら試してみては如何でしょうか。
では、良い週末を!!
本日は当ブログをお読みいただきありがとうございました。
押上 錦糸町 鍼灸院 びわの葉治療院です。